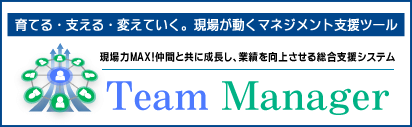【「購入率」は分解できる(前編)~AIDMAとAISCEASで読み解く“勝てる確率”~】の続編です。
https://km.kando-m.jp/news/mm1480/
前回のメルマガでは、
AIDMA(アイドマ)やAISCEAS(アイセアス)といった購買行動モデルをもとに、
「購入率とは、段階ごとの通過率の掛け算である」という話をしました。
この構造を知ると、私たちはもう「なんとなく売れた/売れなかった」では済まされません。
売れる・売れないには理由があり、売れないのはどこかのプロセスに詰まりがあるということです。
だからこそ、「具体的にどこが弱いのか?」「どうすればそれを見える化できるのか?」を考える必要があります。
特に、営業のプロセスは売れない理由が解りにくく、
「ライバルの方が優れているから?」「価格が安いから?」・・・・・・と、外的要因に逃げてしまいがちです。
それでは、売れるものも売れません。
ここで活躍するのが、弊社開発のSFA「Team Manager」です。
■購買モデルと営業プロセスはリンクしている
AIDMAやAISCEASの各ステップは、そのまま営業のプロセスにも置き換えられます。
たとえば:
A(注意・認知) → メルマガ配信、展示会、SNS投稿など
I(関心・興味) → サイト閲覧、資料請求、問い合わせ
S・C・E(検索・比較・検討) → 提案・見積・社内稟議など商談過程
A(行動) → 契約・発注
S(共有) → クチコミ、レビュー、リピート・紹介
つまり、「購買モデル」は顧客の心理的ファネル(※)であり、
「営業プロセス」は企業側の行動ファネルなのです。
※ファネル:顧客が商品やサービスを認知してから購入に至るまでのプロセスを図で表したもの
この二つが噛み合ったときに成果が出ます。
■Team Managerでできる“構造の見える化”
Team Managerを使えば、以下のような「構造の可視化」が実現できます:
(1)どのフェーズで案件が止まっているかを一目で把握できます
→ お客様の比較・検討段階で競合に負けているなら、提案内容やタイミングを見直す必要があります。
(2) 失注理由の蓄積と傾向の把握ができます
→ 興味は持たれたが購買には至らなかった案件を整理すれば、「関心→欲求」の壁が明らかになります。
(3)個人任せではなく、チームで支援できる体制を構築できます
→ 誰がどの業種に強いか、過去の類似案件は誰が対応したかなどの情報を共有すれば、“文殊の知恵”で対応できます。
(4) 行動だけでなく、考え方も言語化できます
→ 日報や活動報告の中に「気づき」や「打ち手」が自然と記録されていくことで、全体のナレッジが蓄積されます。
■改善は“勘”ではなく“構造”から
Team Managerの本質は、単なる報告ツールではなく、
「改善のヒントをチームで見つけて、チームで実行できる状態」をつくる仕組みです。
今、営業や販促で成果が出ていないと感じる場合、
「AISCEASのどこで詰まっているのか?」という問いを立ててみてください。
そしてその問いに答えるために、Team Managerで日々の活動を記録・共有し、分析してみてください。
それは、「売れる仕組みづくり」につながる一歩になります。
■本日の教訓
勘に頼らず、構造を見える化することからチームの進化は始まる。